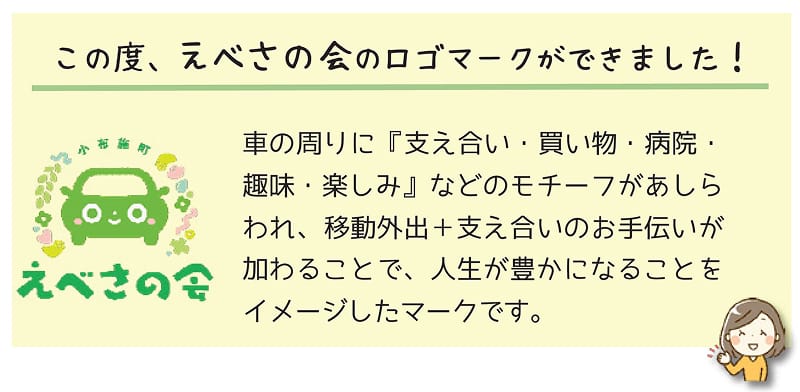「地域助け合い基金」助成先報告
移動外出・付き添い支援 えべさの会
長野県小布施町

助成額
150,000円(2024/08/15)助成⾦の活⽤内容
本助成金を利用して、2024年7月から活動を開始する移動外出・付き添い支援”えべさの会”を、広く多世代の住民に知ってもらいたいと思っています。
地域で支え合う移動外出・付き添い支援を考える会“えべさの会”では、暮らしを豊かにする移動外出について学び、「出かけることで元気になる」を合言葉に、地域住民が主体となった移動外出・付き添いを軸とした支援を行います。対象は、ひとり暮らし等でお出かけに困りがちな高齢者だけでなく、障がいのある方や小さなお子さんを抱えた親御さん等、広く柔軟に支えていきます。また、“足としての移動外出”という支援に加えて、安全に外出するための付添い支援と、関わる中から見えてくるちょっとした生活の困りごとへのサポート、一緒に出かけ交流することから生まれるつながり等まで、生活支援の中にある移動外出として包括的に考えていきます。そして、利用される方だけでなく、活動する協力会員にとっても、えべさの会への取組みが、役割や生きがいとなり、お互い様の「ありがとう」という言葉や気持ちから元気になる活動を目指します。具体的な助け合い活動の内容としては、①買い物や通院等の移動外出・付き添い支援、②生活物品等の運搬・整理収納、③雪かき、④話し相手、⑤電池電球の交換、⑥電気機器等の操作補助、⑦乗り合わせての交流外出支援、などです。
本事業の特徴は、自治体主導ではなく、地域住民が主体となって運営を行う「住民互助による移動支援サービス」になります。運転停止後に趣味や社会参加の外出頻度が減少することは多くの報告がされており、地域に在住する様々な対象者の“足としての移動外出”手段を、住民が主体となって地域で新たに創出できることは極めて重要と考えます。また、“足としての移動外出”という支援に加えて、安全に外出するための付添い支援と、関わる中から見えてくるちょっとした生活の困りごとへのサポート、一緒に出かけて交流することから生まれるつながり等、生活支援の中にある移動外出として包括的に考えることで、地域づくりに繋がると考えます。さらに、利用する側だけでなく、活動する協力会員にとっても、本事業への参加が、役割や生きがいとなり、活動を通して「顔なじみ」の関係が広がり、地域のつながり、コミュニティが広がることを期待しています。これらは総じて、地域住民の健康や幸福に寄与すると考えます。
活動報告
活動の変化
このたびの助成金を活用し、「えべさの会」のロゴマークを作成し、車両用のマグネットシートを制作しました。これまで、私たちの活動は地域内で徐々に広がりを見せていましたが、統一感のあるシンボルがなかったため、認知度を高めることが課題となっていました。2024年12月に完成したロゴは、えべさの会の理念を象徴するものとして、多くの方々に親しまれています。そして2025年3月、車両にマグネットシートを貼付することで、移動支援の車両であることが一目で分かるようになり、地域の皆様に安心感を与えるとともに、新たな協力者や利用希望者からの問い合わせにつながりました。
この活動を通じて、地域に新たなつながりが生まれました。ロゴがあることで「えべさの会って何?」と興味を持つ方が増え、利用者だけでなく支援者の輪も広がっています。協力会員の方々からは、「ロゴがあることで活動への誇りを感じるようになった」「車両にシートが貼られていることで、移動支援の車であることが周囲に伝わりやすくなり、活動しやすくなった」との声が寄せられました。また、利用者の方々も「ロゴを見かけると安心する」「親しみが湧いて相談しやすくなった」と喜んでくださっています。
進めるうえでの課題
「えべさの会」は、地域住民が主体となって移動・外出を支援する仕組みですが、立ち上げから現在に至るまで、さまざまな課題に直面しました。まず、支援を必要とする人々に対して活動を知ってもらうことが最初の大きな壁でした。行政のサポートを受けながらも、地域の高齢者や移動に困難を抱える方々に「こんなサービスがある」と伝え、利用を促すための地道な広報活動が求められました。ロゴマークやマグネットシートの導入によって、この課題は少しずつ解決されつつありますが、今後も継続的な周知が必要です。
また、協力会員の確保・維持も重要な課題です。現在、支援活動を担う協力会員の方々は高齢者が多く、将来的な担い手の確保が求められています。仕事や家庭の事情を抱える世代にも無理なく参加してもらえるような仕組みづくりが必要です。さらに、支援の範囲が移動にとどまらず、生活のちょっとした困りごとにも広がる中で、どこまでを支援対象とするのか、その線引きについても話し合いを重ねながら模索している状況です。
地域の助け合いを全国へ
「えべさの会」が目指しているのは、単なる移動支援ではありません。移動の困難を解消することは、外出の機会を増やし、人とのつながりを生むことにつながります。買い物や病院への送迎だけでなく、「ちょっとおしゃべりしたい」「この用事を手伝ってほしい」といった日常の小さな要望に応えることが、利用者の心の支えとなり、地域の活力にもつながるのです。利用者の方から「気軽に頼める場所ができて、本当にありがたい」「移動を助けてもらうだけでなく、会話が楽しい」といった声をいただくたびに、この活動の意義を改めて感じています。
全国には、移動に困る人がいる一方で、「少しなら手伝える」という気持ちを持つ人もいます。その二者を結びつける仕組みを作り、地域の中で「お互いさま」の意識を育てることが、私たちの目指す未来です。「えべさの会」は、まだ小さな取り組みですが、この活動が全国各地の助け合いの輪を広げる一助となることを願っています。私たちはこれからも、地域の力を信じ、住民主体の支え合い活動を続けていきます。
今後の展開
「えべさの会」が目指しているのは、ただの“移動手段の提供”ではありません。私たちは、移動をきっかけに生まれる“人と人とのつながり”を大切にしています。病院や買い物に行くことも、送り迎えをすることも、その一つひとつが会話の種になり、「誰かが気にかけてくれている」「頼っていい場所がある」という安心感を地域にもたらしています。支援を受ける側も、支える側も、互いの存在を通して元気をもらえる一それこそが、えべさの会の活動の真髄です。
「ちょっと手伝ってもらえれば外出できる」「誰かと話すことで心が軽くなる」一こうした声に耳を傾けながら、私たちは地域の暮らしを支える“町の縁側”のような存在でありたいと考えています。この活動を通じて、一人ひとりの住民が自分らしく暮らし続けられる町、誰もが役割を持って支え合える町づくりに貢献したい。えべさの会には、そんな未来をともに描く仲間が少しずつ増えています。
今後は、より多様な世代の方にも参加していただけるよう、活動の柔軟さや楽しさを発信していきたいと考えています。また、各地区ごとに“顔の見える助け合い”が育まれる仕組みを模索し、住民一人ひとりが「自分の地域は自分たちで守る」という誇りを持てるような活動へと広げていきたいと思っています。
えべさの会の取り組みが、全国の「助け合いの芽」のひとつとなり、それぞれの地域で花を咲かせていくことを願っています。私たちはこれからも、地域に根ざしたあたたかなつながりを育みながら、一歩一歩、歩んでまいります。
添付資料